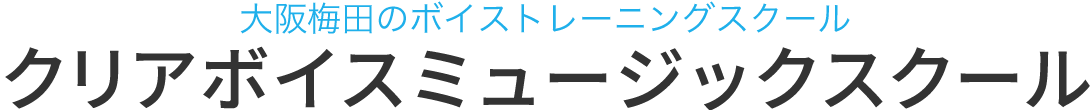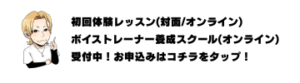2025.07.06ボイストレーナー論
ボイトレにおける「〇〇メソッド」は“机上の空論”?ボイストレーナーに最も必要なスキル
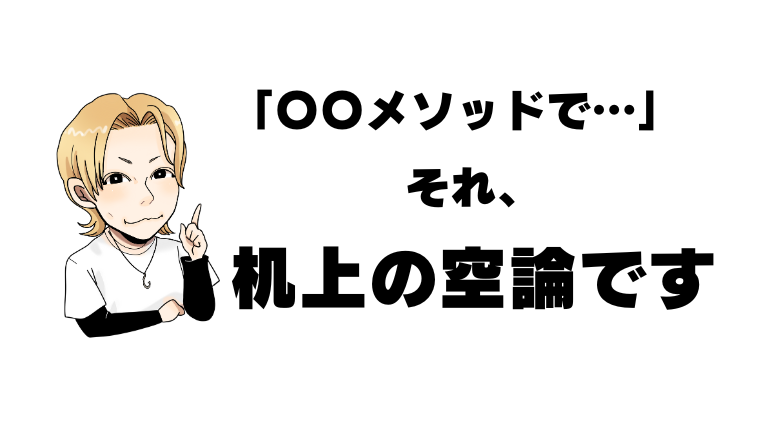
あなたの声のセカンドオピニョン、クリアボイスミュージックスクールのジウコトモニタ(谷本恒治)です。
ちょこっと「ボイトレ」などのキーワードでググると見かけますよね、
〇〇メソッド
生徒さんはあなたの指導が何メソッドなのかはどうでもいいことです。
ケガをしてお医者さんに傷口を縫ってもらったこと、あります?
それ、何縫いでした?
どうでもいいでしょ?
今回はその〇〇メソッドがクソの役にも立たないというお話。
※メソッドそのものを否定するのではありません。メソッドそのものを教える意味がない、というお話です
 |
ジウコトモニタ(谷本恒治) クリアボイスミュージックスクール代表 数多くのプロミュージシャンのボイストレーニングを担当し、 TVなどでも紹介される。 発声のメカニズムなど確かな知識に基づいた的確な指導で、 現在も全国各地から受講生が集まっている。近年はボイストレーナーの 育成にも力を入れている。 |
ボイストレーナー養成スクールでの一コマ

理論を習得してめちゃくちゃ優秀に!
僕が運営するボイストレーナー養成スクールでは、半年間のカリキュラムのうち、前半3か月はお勉強、後半の3か月は実践訓練、という内容になっています。
そして2025年4月生の後半の実践訓練が始まったのですが…
さすがにみなさん優秀!
実際に生徒さんの発声を聞いてもらい、「この生徒さんにどんなエクササイズを提案する?」というディスカッションを行っていくんですが、みなさん次々と、「こんなエクササイズはどうでしょう?」と意見が飛び交います。
キャリア15年のベテランの方、本場ハリウッドでも指導経験のある方など、現役のボイストレーナーの方に混じって、未経験の方もいらっしゃるんですが、全くヒケを取らず、「こういう印象を受けるのでこういうエクササイズが…」と、とても優秀な意見を出してくれます。
我ながら「前半の理論のカリキュラムが相当イケてるんだな」と自画大自賛。
決定的な弱点が…
が、そのアイディアがどれも、「いや、理屈上はそうなんだけど…」というもの。
そう。
これが世のボイトレが「机上の空論」たる所以。
理論というのは、「筋肉はここに付いている」「その筋肉はこう動く」という“事実”でしかありません。
事実を知ったとて、生徒さんの声を改善できることはないのです。
なので、一つ一つのアイディアに、
「いや、そのエクササイズをこの人にやるとこうなるよ」
「いや、この人にとってはそれは要求が高すぎるよ」
と、否定のアイディアを出していく(もちろん修行としてあえて否定していく要素もあります)
するとみなさん、「うーん…」と行き詰る。
この“一度行き詰る”を経験しておかないといけないのです。
それは何故か…
「やべ、机上の空論になってたぞ…」という方、今ならまだ間に合う!こちらへ
実はトレーナーに最も必要なスキル
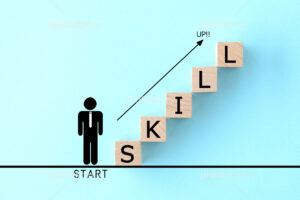
瞬発力
当然、実際のレッスンの現場で、「ちょっと待ってね、次のエクササイズを今考えてるから。うーんっと…」
という訳にはいきません。
僕がもし生徒なら、
「あの、帰っていいいっすか?」
と言います(笑)
生徒さんの声を聞き、瞬時にエクササイズを判断する。
例えば体験レッスンでいうと、まず最初にアーというだけでスケール(音階)を上下してもらうのですが、このスケールの中盤にはもう次のエクササイズが浮かんでいる、というのが理想です。
対応力
もちろん僕も毎回毎回、100%正しいエクササイズが選択できるかというと、そうではありません。
「こうだ!」と思ってエクササイズを入れた瞬間、「あら、そうなるのか…」ということは大いにあります。
そこで、「じゃあこれは?」と、すぐに次のエクササイズに対応できる力が必要になります。
そのためには「こうやったらこうなる」あるいは「そうならないなら何故ならないのか」「それをどう修正するのか」という豊富な知識が必要になるのです。
そこで先述のディスカッションがとても重要になってきます。
あえて僕が意地悪して、受講生が提案したエクササイズを「できない生徒」を演じてみせます。
「それじゃあこうなってしまうよ、じゃあ、次どうする?」
このやり取りを繰り返すことで疑似的にレッスンの経験を積んでいく。
ボイストレーナー未経験の方にとっては、このカリキュラムで、トレーナーとしての活動をスタートした時点ですでに「経験者」としてのスキルを手に入れる訳です。
誰もが喉から手が出るほど欲しい“経験”のスキルを、未経験の方でも手にできる!早速こちらへ
机上の空論レッスンの結末

あなたは車の整備士?教習所の教官?
僕がざっと知る限り、あまりこの部分に特化したトレーナー養成カリキュラムはないかも分かりません。
ぶっちゃけ、理論はググりゃ勉強できます。
でも実際に生徒さんを前にした時に必要なのは理論ではありません。“聞く力”“洞察力”です。
僕はよく、「ボイストレーナーは車の整備士ではない」という話をします。
ブレーキの効きが悪いからブレーキパッドを交換しましょう
これは整備士の仕事です。
これはレッスンとは言いません(断言)。
ただの“事実の伝達”です。誰でもできます。
“事実の伝達”ではなく“レッスン”をしましょう
私たちはボイストレーナーです。自動車でいうと教習所の教官です。
先ほどのブレーキの例で言うと、
A君の場合
「君は注意力が散漫であちこちよそ見をしながら運転している傾向にある。なので障害物や子供の急な飛び出しに対する反応が遅れて急ブレーキを踏まないといけなくなるんだよ。急ブレーキはブレーキパッドの消耗を早めるから、運転中は周囲を良くみて、早めのブレーキを踏めるようにしようね」
B君の場合
「君はうう点操作が一つ一つ荒いね。ハンドルをガッと急に切る、ブレーキもアクセルもガッと強く踏み込みすぎる。そうすると隣に乗っている彼女はその度にガクンガクンなって車酔いするかも分からないよ。運転操作は優しくしようね」
これが“レッスン”です。
事実を伝える“メソッドテラー”ではなく、きちんと一対一で向き合う“指導者”でいるよう努めましょう。
ただの“メソッドテラー”から“一流の指導者”へ。今すぐこちらから
生徒さんと向き合う指導者でいるには?

メソッドを知れば知るほど、それを振りかざしたくなる気持ち、分かります。
どうです?僕(私)、詳しいでしょ?
クッソどうでもいいです(笑)
当然一人一人と向き合うために知識は必要です。
でももっと必要なのは、声からその生徒さんの“意図”をくみ取れるかどうかです。
これには実は特別なスキルが必要になります。
僕のボイストレーナー養成スクールでは、前半の理論の勉強に加え、特に後半の実践訓練でここ、「生徒さんの発声がどうなっているか」という“事実”ではなく、「生徒さんが何をしようとしているか」という“意図”を聞く力を身に付けていただきます。
時間の許す限り、できるだけたくさんの声を聞いてもらい、アイディアを出し、それを否定され(笑)、次のアイディアを出し、と繰り返し、「トレーナーとしての疑似経験」を積んでいただきます。
正直、このカリキュラムは全国で当スクールだけです。
今一つ生徒さんに手ごたえをつかんでもらえない方、生徒さんがあまり増えずに悩んでいる方、ボイストレーナーになりたいけど自信がないという方。
新たな一歩を踏み出してみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
是非他の記事もご覧ください。
マンツーマンレッスン(対面・オンライン)/ボイトレ通信講座/ボイストレーナー養成コースのお申込みはコチラ
クリアボイスミュージックスクール
講師 ジウコトモニタ
☎ フリーダイヤル 0120-103-326
(受付時間13:00~21:00、レッスン中は出られない場合もございます。ご了承ください)
✉ clearvoicemusic@gmail.com
Category
New Article
Archive
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月